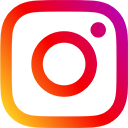【ワインに合う音楽】とは、そもそもなにか?
ワインを飲むときに音楽を選ぶことのすすめ

ワインと音楽の関係は、たとえばビールと音楽、とか、ウォッカと音楽、日本酒と音楽…etc.に比べて、親密であるような気がしないだろうか。
でもなんとなく、ウィスキーと音楽だったら、それはそれで密接なような気もする。実際、私はワインよりウィスキーの方をよく飲むので、音楽なしでウィスキーを飲むことはあんまり考えられない8きっと文字どおり、「味気ない」だろうと思う。
BGMは人間に驚くほど影響を与えている

引用は『ドビュッシーはワインを美味にするか?音楽の心理学』ジョン・パウエル著 濱野大道訳 早川書房 2017年。
ここには、ワインと音楽の関係について調べるためにされたいくつかの実験が載っている。これらの実験では被験者にBGMについての言及はせずに行われている。
結果を要約すると、以下のことがいえそうだ。
- 音楽が直接的にワインの味の感じ方にも影響を与える。(音楽の印象に味覚が左右される)
- ポップスよりもクラシック音楽の方がより優雅で裕福な気分に浸れる。(選ぶワインも高価なものになりがちである)
- 音楽は、多く「心地よい」感情を引き起こす。(そのように作曲されているものに限る)
- 音楽と状況の「適切性」について人間は驚くほど反応する。(整合性をとろうとする行動をとる)
- 通常それらはほとんど意識されないままに起こる
ノース教授とハーグリーブス教授は、スーパーマーケットの通路の端にあるワイン陳列棚の上にスピーカーを設置し、音楽の種類が客の購買行動に与える影響について実験を行った。ワインの棚は全部で四つあり、どの棚にも片側半分にフランス産ワイン、片側半分にドイツ産ワインが置かれている。それぞれの棚には価格や甘さ/渋みが似たものが置かれており、両国のワインが公平に戦う場が用意された。
「ドビュッシーはワインを美味にするか?」 p20
あとはときどき音楽を変え、どの音楽が流れたときにどのワインが売れたかを観察するだけでよかった。
結果は驚くべきものだった。
スピーカーからドイツの音楽が流されたとき、ドイツ産ワインはフランス産よりも二倍の勢いで売れた。
一方、フランスの音楽が流されたとき、フランス産ワインはドイツ産よりも五倍の勢いで売れた。

心理学者チャールズ・アレニとデイヴィッド・キムによって行われた別の実験では、ポップスとクラシック音楽がワインショップの客の支払金額にどのような影響を与えるかが調べられた。…(略)クラシック音楽は明らかに客をより優雅で裕福な気分にさせた。購入本数に変化はなかったものの、クラシック音楽が流れたときに客はより高いワインを選んだ。それも、少し高いワインなどではない。購入価格はなんと三倍以上に跳ね上がった!
「ドビュッシーはワインを美味にするか?」 p20-21

ある実験では、数グループに分かれた参加者が無料のワインを愉しむあいだに、四種類の異なるBGMが流された。バックにかける音楽として選ばれた曲調は、①力強くヘビー、②繊細で上品、③元気でフレッシュ、④甘美でソフト、の四つ。もちろん、参加者にはBGMが重要であることを知らされず、通常のワイン試飲会かのように実験は進められた。試飲後にワインの味が「ヘビー」「上品」「フレッシュ」「メロウ」のどれに当てはまるかを評価してもらうと、参加者たちに味と音楽の曲調を結びつける傾向があることがわかった。…(略)実際のところ、どの音楽をかけたときにも、試飲用に出されたワインはすべて同じカベルネ・ソーヴィニヨンだった。さらに、参加者は無料のワインを愉しむことに夢中で、BGMにはほとんど気を留めていなかった。
「ドビュッシーはワインを美味にするか?」p.21
表題の、いかにもワインに合いそうなドビュッシーの音楽が実際のところワインを美味にするのかという影響について本書では深く考察されておらず、それどころか同じく同一のワインでBGMを変化させた実験では、ワーグナーに負けている。(P.22) ドビュッシーの音楽がワインの味覚の印象を左右することはあっても、それが一概に美味にするか、ということとは別のことのようである。
音楽を選ぶことも、ワインの楽しみ

以上の実験結果から考えあわせると、結論としては、BGMにはワインの味を変える効果があることは、人間である以上まず間違いない。そして、あるワインに合う音楽を選ぼうと思ったら、いろいろと自分で試してみるしかない、ともいえそうだ。クラシック音楽をかけるとリッチな気分になる、音楽の曲調に印象が左右される、とわかっても、それが自身の求める味覚体験であることとはまた一線を画すものであるはずだからだ。
ただやみくもに試すのではなく、そこにはヒントがある。
概して物事は、ある一定の知識や経験がたまったときに、ふいにモノの方から語りかけてくる瞬間というものがある。ワイン(味や香り、ラベルまでのワインをワインと成すものすべて)と音楽(ジャンル、演奏される楽器、演奏者、歌詞、作曲家、時代etc.)はそのどちらも膨大な量の知識を有する豊かな土壌がある。
そのものが語りかけてくるものがより多く聞けるようなればなるほど、自分というフィルターを通してそれぞれ個人的嗜好に沿ってベストなマリアージュを選ぶことが可能になると思う。(このワインには、王道クラシックがいいかな、それともジャズなんていいんじゃないか…etc.)
そして、それらを選ぶ過程すべて、ワインを楽しむ時間を豊かな経験にかえてくれるといえるはずだ。
ぜひ試してほしいBGMは、モーツァルトとハイドンのピアノソナタ
そんな非常にパーソナルでクリエイティブな行為であるBGM選びに、私なりにひとつおすすめを紹介してみたいと思う。
ここまで読んでくださった皆さんにぜひ一度試してみてほしいと思うのは、モーツァルトとハイドンのピアノソナタだ。それも、マルク・アンドレ・アムランの演奏が至極である。

なんといってもモーツァルトもハイドンも、筋金入りの宮廷音楽家。優雅で、不安の色を見せない。
バッハのように神の荘厳さにひざまずいたり、ベートーヴェンのように自らの運命に立ち向かったり、ショパンのように身を削るほど激しい思いを抱いたりしない。
あくまで当時の貴族階級のために演奏されることを想定したモーツァルトやハイドンの音楽はそれだけで優雅な気分に浸ることができ、アルコール界の気高さランキングベストワンに輝くワインにはぴったりだと思う。
また、ソナタはソナタ形式というルールの中で作曲される手法が用いられているのため、安心して聞いていられるというのも、おすすめの理由。やっぱり主役はあくまでワインなのである。ラフマニノフやシューベルトを聞いてその旋律的な美しさにうっかり聴き入ってしまってはいけない。あくまで空間を邪魔しない、壁の華のような相乗的効果の見込める音楽が適していると思う。
しかしたとえば、先の実験によれば、フランスのワインを飲む際にはドビュッシーのようなメロウなフランスの音楽、イタリアのワインを飲む際にはロッシーニのようなふくよかな音楽が合うのではなかっただろうか?と思われるかもしれない。
心配はいらない。ピアニストのマルク・アンドレ・アムランは、当代きってのスーパーヴィルトゥオーゾと称され(本人はそう言われるのは好まないとしている)、演奏至難な超絶技巧をまるで小鳥がステップを踏むように軽やかに打鍵し、奇のてらいもなくそこに音楽の本質を出現させる。そのくせ子供が好んで弾くようなモーツァルト・ハイドンの古典派のソナタでも、毎回卒倒するほどかっこよく決めるので、結論オールマイティーなのである。最も軽いワイン(打鍵)~重厚なワイン(打鍵)までそこにはすべてにマッチしうるものが内包されている。
演奏至難、ゴドフスキーの「ヨハン・シュトラウスⅡ世による酒・歌・女による交響的変容」
また、youtubeで聴けるアムランの演奏として、レオポルド・ゴドフスキー(1870-1938)の~ Symphonic Metamorphosis on Wein, Weib und Gesang~(ヨハン・シュトラウスⅡ世、酒・女・歌による交響的変容)もおすすめしたいと思う。ゴドフスキーは、超絶技巧の作曲家で、他の作曲家のパラフレーズでよく知られるが、そのどの作品も演奏至難として、そもそも弾けるピアニストがごく限られるためにほとんど演奏される機会に恵まれないというトンデモ的稀有な存在である。
そんなゴドフスキーもアムランが弾けば、まったくその難解さを感じさせない。曲そのものが語りかけてくるものをシンプルに純粋に、そのまま聴き手に差し出してくれる。その中でもヨハン・シュトラウスⅡ世によるこちらの演奏は10分ちょっとの小品であるが、限りなくその流れは美しく、文字通り人生の喜びに満ちている。ぜひ今日はワインを1本開けて、この曲と共にしばし日々の心配事は忘れてください。
マンジャーレ・カンターレ・アモーレ~食と歌と恋と~

ところでイタリア人の国民性を表すとして、“mangiare, cantare, amore.” (食べる・歌う・愛する)という言葉がある。「人生を謳歌する」という意味だ。複雑に見える世の中だけど、今この瞬間、大事なことはシンプルで、それほど多くない。人生には限りがある。
「ワインに合う音楽とは何か?」という命題からずれてしまったが、味覚なのか、香りなのか、音楽なのか、舌触りなのか、それらが判別されずに複合的にまざりあったものを味わう、つまりは五感をフルに使って楽しむことこそが人生を豊かにするのではないのか。と大きく提案して終わりたいと思う。
ここまで読んでくださった方へ。
読んでくださりありがとうございました。ワインのまた別の楽しみ方を、イタリアの工房で職人の制作する保冷ボトルホルダー、Freezerino(フリゼリーノ)の物語とともにご紹介しています。よければTOPページから他の記事もあわせてお楽しみください(^^)
(Top Image : Jos Speetjens from Unsplash)
- 12,000円 [税込]
【ピットーネレッド・ストレート型】 赤のラミネート地に黒でスネイク柄のエンボスが施されたデザインです。イタリアで人気のモデルです。 一般のボルドー型(赤ワインや白ワイン等)のワインに対応しているサイズのフリゼリーノです。 なで型のボトルでも、横9㎝まででしたら入れていただくことができます。 アクセサリーとして別売のチェーンをジップにとりつけることができます。 持ち手としては耐久しませんが、アクセントとなり華やかさが増します。 ぴったりした形状のボトルをお選びいただくこ…
- 12,000円 [税込]
【イントレチャート・ストレート型】 プラチナゴールド地に、細かく編地の箔押しがされています。編地のエンボスにより、光が四方に飛び交いキラキラと輝くような見た目が印象的です。 光の当たり方で写真の印象が変わりますが、すべて同じ商品です。 一般のボルドー型(赤ワインや白ワイン等)のワインに対応しているサイズです。 なで型のボトルでも、横9㎝まででしたら入れていただくことができます。 アクセサリーとして別売のチェーンをジップにとりつけることができます。 持ち手としては耐久し…